(*) 諸聖人の日とも。キリスト教において全ての聖人と殉教者を記念する日で、カトリックでは11月1日。その翌日は「死者の日」(万霊節)で死者の霊を祀る記念日。フランスでは万聖節は祝日に定められており、この時期に近親の墓参りをする習慣があるそう。
ジルは母の姉妹をたずねようとするが、彼には叔父もいた。父の兄弟であるオクターヴ・モーヴォワザンは輸送業で成り上がった金持ちであったが、4ヶ月前に死んでおり、ジルはその莫大な遺産の相続人であった。相続にあたっては、ユルスュリーヌ河岸にある邸宅に若い未亡人コレットとともに住むことが条件に付けられていた。そしてジルの手には、パスワードの組み合わせが不明の金庫の鍵が渡される。
両親を失った悲しみが瘉えないながら、ジルは女性たちへの関心でも心が揺れる。しかし、彼の心内にはお構いなしに、叔父オクターヴを敵視していたラ・ロシェルの名士連中 Syndicat の圧力がかかってくる。そして、一つの事件が起こったのを機に事態は大きく動き始め、ジルの心境にもさまざまな変化が生じる。
***
シムノンはフランス南西部の港町ラ・ロシェルを舞台にした小説をいくつか書いている。邦訳のある『ドナデュの遺書』や『帽子屋の幻影』のほか、«Le Haut Mal»(癲癇の発作)、«Le Clan des Ostendais»(オーステンデの一族)など。『離愁』でも、戦火を逃れて行き着いた先はラ・ロシェルだったか(*)。
(*) シムノンは1932年から1945年までのあいだ、ラ・ロシェルに近いマルシリーやニウル=スュル=メール、フォントネー=ル=コントなど、シャラント地方、ヴァンデ地方と呼ばれる地域に住んでおり、本作もフォントネー=ル=コント在住の時に執筆された。Michel Carly というシムノン研究者が «Simenon, le bonheur à La Rochelle»(«Simenon et les secrets de La Rochelle» の復刊版?)という本を書いているので、機会を設けて読んでみたい。
«Le Voyageur de la Toussaint»(万聖節の旅人)も、そういった「ラ・ロシェルもの」の一つ。本作では、大時計塔 Grosse Horloge やエスカル通り rue de l'Escale、アルム広場 place d’Armes(旧練兵場、現在の名称はヴェルダン広場 place de Verdun )など市内に実在する場所のほか、名称こそは架空だが、実在の通りがモデルとなっていると思しきところ(例えば、モーヴォワザン家の邸宅と会社があるユルスュリーヌ河岸 quai des Ursulines は市内を流れる運河沿いの通り、モベック河岸 quai Maubec がモデルとみられる)を主人公たちが歩く。シムノンが実際に観察した街並みの様子が、かなり詳しく小説の中に反映されているよう。
突然両親をなくし、かつにわかに莫大な遺産と事業を継いで、名士連中のようなこれまで接したことのなかった階級の人々と対峙し、運命にひたすら翻弄されるだけであれば、主人公のジルはただ「ノルウェーから来た遺産相続人」と呼ばれるだけに終わったかもしれない。
けれども、ジルは激変した身の回りの状況に動揺しながらも、自らの意志で事業の継承者となり、またある出来事をきっかけに生前の叔父オクターヴの足跡をたどることで、その秘密だけでなくオクターヴの裡に去来したであろうことに気づき、延いてはジル自身の本当の心情、願望を自覚していく。
生前は従業員や町の人々だけでなく、ラ・ロシェルの実力者たちにも恐れられ、死んでもなお彼らの生活に影響を及ぼす亡霊、オクターヴ。一方で、貧乏ながらも自由な生き方を選択した父の息子であり、内気で臆病だった青年ジル。しかし彼には、ラ・ロシェルという土地にあえて縛られながら立身出世した叔父の手腕だけでなくその風貌、とくに寡黙な様子にどこか重なり合うところが見られる。そのようなジルだからこそ、物語の中の謎を解明することができるのかもしれない。
しかし、何よりもジルを突き動かすものは、心内でさまざまに形作られ、確信を強めていく愛情にほかならない。ミステリーの筋書きではありつつ、本作はシムノンならではの恋愛小説だと思う。
死者たちの想い出や足跡をたどる「万聖節の旅人」ジルが最終的に選ぶ道は......
***
シムノンにしてはわりあい息の長い作品だが、物語は綿密に構成されているというか、本作以上に分量のある『ドナデュの遺書』に比べると途中で冗長な部分もみられず、つたない語学力でも最後まで読み進めることができた。一方で、エピローグにはどこかふだんのシムノンらしくない結び方を感じたが、それはあらかじめ映画化を見越して執筆されたからなのだろうか、と思ったり。
〔本書の構成〕
- 第1部:密航者(全6章) Le Passager clandestin
- 第2部:エスナンドの結婚(全7章) Les Noce d'Esnandes
- 第3部:ロワイヤンでの散策(全7章) La Promenade à Royan
- エピローグ:フォントネーの夜 La Soirée de Fontenay
〔余談〕
本作は1943年にマルセル・エメ脚本、ルイ・ダカン監督で映画化されているほか、2005年にもテレビドラマ化されている。いずれも一度は観てみたい。
Georges Simenon, Le voyageur de la Toussaint, 1941
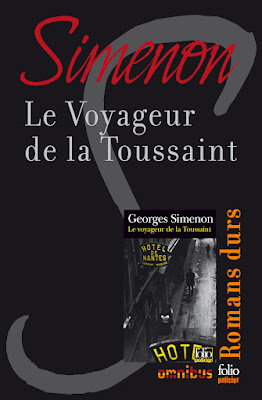
2 件のコメント:
非メグレ作品で題名のみ知っていたのですが、この記事を拝見して読んでみたくなりました。(「謎のピクピュス」もまだ買えていませんが・・・)
ロシアのok.ru/video で1943年のモノクロ映画が見られます。(最近は登録またはログインしろと要求されますが、こんな時局なのでやらないで close しても少しの間は見続けられます)製作時はナチ占領下だったのによくもこれだけの映画が作れたなーと感心します。音楽のヴァイオリンの音色もロマンチックです。
https://ok.ru/video/3193734826512
ネット上に「シムノンと映画」という永田道弘さんの論文があります。やはり検閲が厳しかったようですが、それでも完成されています。それに比べると日本の戦中期は悲惨で、文化的にも不毛の砂漠だったと思います。
cogeleauさん、拙文をお読みくださりありがとうございます。
映画のサイトもご案内くださりありがとうございます。
私も永田さんの論文を興味深く読みました。ナチス占領下で、厳しい検閲を受けながらも質の高い映画を世に送り出そうとしたのは、単なる商業利益の追求以上に、映画はフランスが誇る芸術文化であるという自負があり、ナチスへの無言の抵抗心もあったのかなと思いました。原作者であるシムノンも、そういう精神をもつ一人だったのではないかと。
コメントを投稿